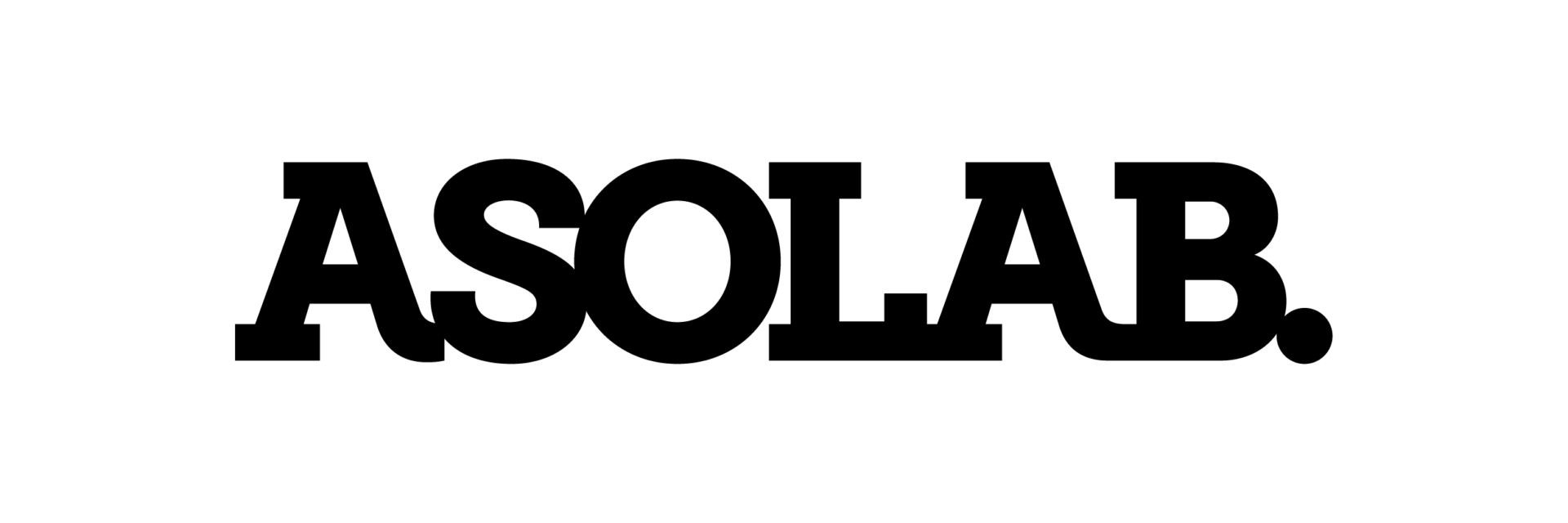ドローンを安全に飛行させるために欠かせないのが「補助者」の存在です。
補助者は操縦者の「もう一つの目と耳」として、周囲の安全を見守り、危険を未然に防ぐ役割を担います。
この記事では、補助者に必要な3つの柱を解説します。
- 公式に定められた役割の理解
- 法律・ルールに関する知識の習得
- 現場での実践的な工夫(スタッフMの実践例)
新人教育用としてはもちろん、社外の方に当社の安全体制を知っていただく機会にもしていただければ幸いです。
1. 公式に定められた補助者の役割
国交省の標準マニュアルや航空法では、補助者に次の役割が求められています。
- 飛行準備と経路の安全確認
離着陸場所や飛行経路を事前に確認し、障害物があれば対処する[※国交省]。 - 常時の監視
飛行中は周囲の空域や地上の状況を監視。気象や風、他の航空機、第三者の侵入などに注意を払う[※国交省]。 - 情報伝達と意思疎通
危険や異常を発見した場合、速やかに操縦者へ伝える。飛行前に連絡手段(声・インカム・合図など)を確認しておく[※国交省]。 - 配置と役割分担
飛行範囲に応じて補助者の数や担当範囲を決める。必要に応じて立入管理と組み合わせる[※国交省]。 - 緊急時対応
不測の事態に備え、着陸場所への誘導や操縦者への報告を行う[※国交省]。
ポイントまとめ
- 法律やマニュアルに基づく「必須の役割」
- 飛行の安全性を守るための最低限のベースライン
2. 補助者に求められる知識と理解
補助者は操縦者の横に立つだけではなく、法律や安全ルールを理解し、現場で判断できる知識が必要です。
- 航空法・関連ルールの理解
- 航空法第132条の86(第三者上空の禁止)
- 飛行許可・承認制度の概要
- 夜間飛行・目視外飛行など、補助者が必須とされるケース
- 飛行マニュアルの把握
国交省「飛行マニュアル」に定められた補助者の役割を理解していること - 現場リスクの基礎知識
鳥・電線・建物・バッテリー温度など、事故につながりやすい要因 - コミュニケーションスキル
操縦者と適切にやりとりするための声掛け、合図、インカムの使い方
ポイントまとめ
- 補助者は法律・ルール+基礎的な現場知識を持っていることが前提
- 「知識があるからこそ現場で判断できる」
3. 補助者の実践例(スタッフMの場合)
ここからは、実際に現場で補助者を担当している「スタッフM」が普段意識していることを紹介します。
新人の方は、これを参考に自分なりの補助者スタイルを築いてみてください。
- 飛行時間とバッテリーの管理
- 飛行ログを作成し累計時間を記録
- 20分を目安に残量を確認し、パイロットに声かけ
- バッテリー交換を補助
- 季節ごとの温度管理にも注意(寒冷時は保温、炎天下では直射日光を避ける)
- 具体的な注意喚起
- 鳥や電線、建物、人や車を常に監視し、状況を声で具体的に伝える
- 「鳥が来ています」
- 「電線近いです」
- 「建物近いです、止まってください」
- 鳥や電線、建物、人や車を常に監視し、状況を声で具体的に伝える
- 鳥への対応
- 鳥が寄ってきた場合は機体を停止
- 周遊が続くときは一度着陸し、鳥が立ち去るのを待つ
- 電線や建物への対応
- 「近い」と伝えるだけでなく、パイロットの意図を確認し、安全を優先して誘導
- パイロットとの連携
- 「これからどこへ飛ばすか」を定期的に確認
- 危険な操作を抑止するため積極的に声かけ
- 操縦環境のサポート
太陽光でプロポ画面が見えにくい場合は影を作る - 撮影業務の補助
点検現場では必要な写真を事前に確認し、撮影が確実に行えるようサポート
ポイントまとめ
- 「公式の役割+知識」に加えて、現場では個人なりの工夫が大事
- スタッフMの例はあくまで一つのモデル。新人は自分に合ったスタイルを見つけることが重要
パイロットの声から学ぶ補助者のポイント
実際に操縦を担当するパイロットからは、補助者に対して次のような声が挙がっています。
- 飛行方法を理解していてほしい
飛行前に「ノーズインで行きます」など方法を共有することがある。補助者がその意味を理解していないと、パイロットは的確なサポートを受けられない。 - 具体的な声かけが必要
「危ない」だけでは伝わらない。
例:「建物まで3m」「電線の手前5m」など、距離や方向を具体的に知らせてほしい。 - 早めの声かけを意識してほしい
操縦者は画面に集中しているため、直前に言われても対応できないことがある。余裕をもって「この先5mで建物が近いです」と伝えるのが望ましい。
こうしたパイロットの声を踏まえると、補助者は「理解」「具体性」「タイミング」の3点を意識することが重要です。
まとめ
補助者は「操縦者のもう一つの目と耳」として、安全な空撮を支える存在です。
法律に基づいた基本的な役割を理解しつつ、必要な知識を身につけ、現場での実践的な工夫を重ねることで、より安全な運用が可能になります。
当社ではチーム体制での安全運用を徹底しています。
これから補助者を務める新人の方は、ここで紹介した基本役割・知識・スタッフMの実践例を参考に、安全第一で現場を支えてください。
株式会社ASOLAB.では、法律に基づいた体制と現場での徹底した安全管理を行っています。
空撮や点検を安全に実施したいとお考えの企業・自治体の皆さまは、ぜひお気軽にご相談ください。
参考資料(国交省公式ドキュメント)
- 国土交通省「無人航空機に係る規制の運用における解釈」
https://www.mlit.go.jp/common/001218179.pdf - 国土交通省「無人航空機の飛行マニュアル(改訂版)」
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html - 国土交通省「無人航空機 飛行の安全に関するガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000002.html - 国土交通省 無人航空機関連情報(制度・安全ルールまとめページ)
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/