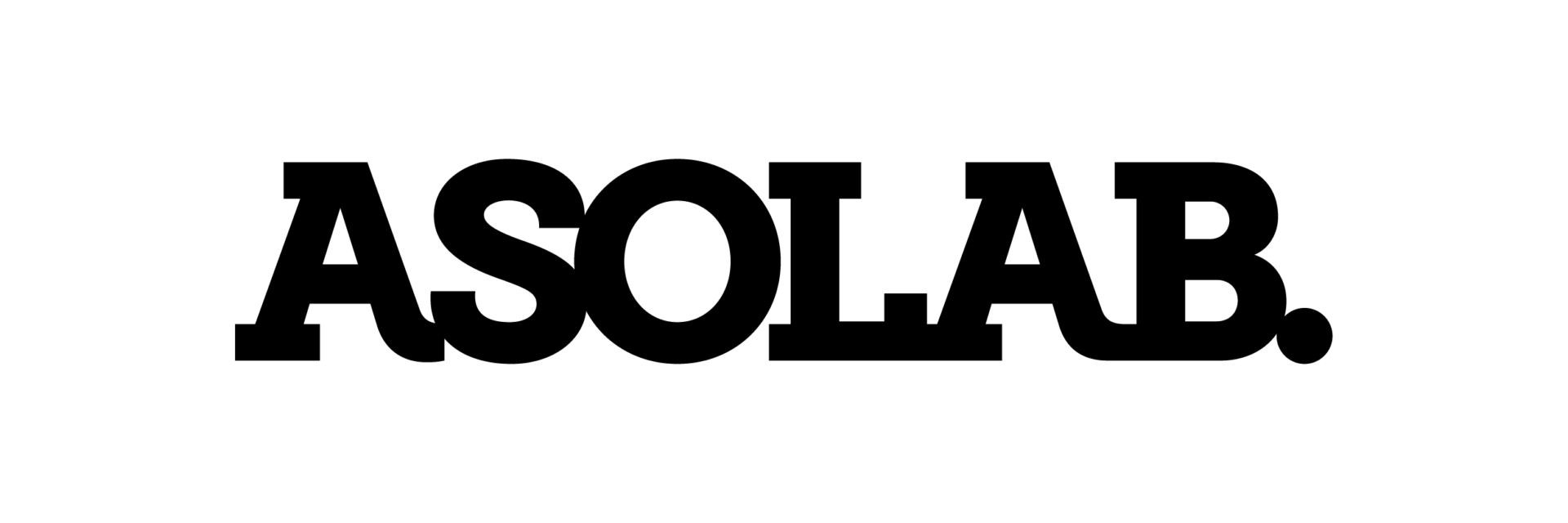ドローン技術の進化と普及により、空からの詳細なデータを手軽に取得できるようになりました。この空撮データを活用した3Dモデル作成は、建設、測量、インフラ点検、エンターテイメントなど、多岐にわたる分野でその重要性を増しています。
そんな中、従来の3Dメッシュモデルとは一線を画す、新たな3D表現技術として「3D Gaussian Splatting (3DGS)」が登場し大きな注目を集めています。まるでその場にいるかのような圧倒的な再現性と、高速なレンダリング性能は、3Dデータ活用の可能性を大きく広げるものとして期待されています。
しかし、「本当に従来のメッシュモデルより優れているのか?」「具体的に何がどう違うのか?」「自分の目的にはどちらが適しているのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ドローンで実際に撮影した同一の空撮データを使用し、従来から広く用いられている「3Dメッシュモデル」と、話題の新技術「3D Gaussian Splatting」の両方で3Dモデルを作成し比較してみます。
従来手法:3Dメッシュモデルとは?
ドローンで撮影した写真から3Dモデルを作成する方法として、長年にわたり活用されてきたのが「3Dメッシュモデル」です。まずはその基本的な仕組みと、メリット・デメリットについて見ていきましょう。
3Dメッシュモデルは点、線、面で立体を表現
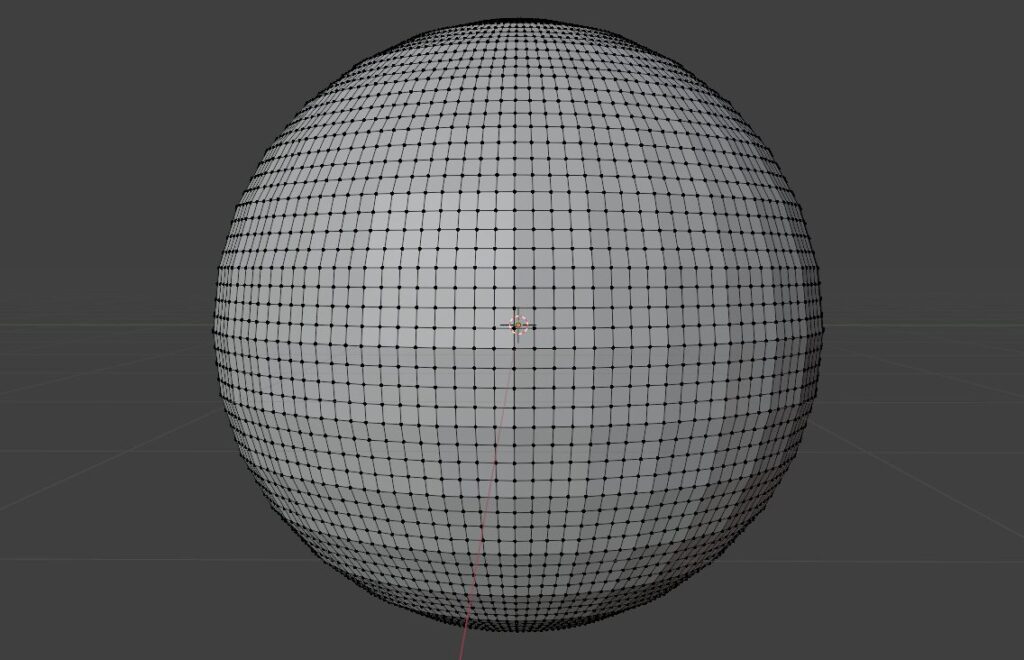
3Dメッシュモデルは、文字通り「メッシュ(網の目)」のような構造で3次元の形状を表現します。具体的には、以下の3つの要素で構成されています。
- 点群: まず、複数の写真から共通の特徴点を見つけ、それを元に無数の点の集まりである「点群」を作成します。
- メッシュ: そしてこの点群の点同士を線で結び、さらにそれらの線で囲まれた「面」を作成し、複数の面によって立体が滑らかに表現されます。
- テクスチャ: 最後に、撮影した写真の色や模様の情報を作成されたメッシュの表面に貼り付けます。これにより、モデルにリアルな質感や色彩が与えられ、見た目が完成します。
メリット:長年使われてきた安定性と汎用性
3Dメッシュモデルが長年にわたりスタンダードとして利用されてきたのには、以下のような明確なメリットがあるからです。
- 高い汎用性と互換性: 従来の3Dモデルは一般的な3Dモデリングソフト、CADソフト、ゲームエンジンなどで直接読み込んで利用でき、特定のプラットフォームに縛られにくいのが大きな強みです。
- 編集・加工のしやすさ: メッシュ構造は、BlenderやMayaといった3Dモデリングソフトで頂点を移動させたり、面を削除・追加したりといった編集が比較的容易です。不要な部分の削除や、形状の修正、他の3Dモデルとの結合などが柔軟に行えます。
- 既存ワークフローとの親和性: 建設、測量、製造といった既存の産業分野では、3Dメッシュモデルを扱うワークフローが既に確立されている場合が多く、導入がスムーズに進められます。また、計測(距離、面積、体積など)も比較的行いやすいという利点があります。
- 豊富なノウハウと情報: 歴史が長い分、インターネット上や書籍などで作成方法やトラブルシューティングに関する情報が豊富に存在します。学習リソースが多いのもメリットと言えるでしょう。
デメリット:再現性の限界とデータ量の課題
一方で、3Dメッシュモデルにはいくつかの課題や限界も存在します。
- 細部の再現性の限界: 特に複雑な形状や、細かい凹凸、木の葉やフェンスなどの薄い構造物の再現は苦手とする場合があります。また、光沢のある表面や水などの透明なオブジェクトの再現も困難です。
- 処理時間と計算コスト: 3Dメッシュモデルの作成には高性能なPCが必要で、特に高精細なモデルを作成しようとすると点群処理やメッシュ生成に非常に長い時間がかかることがあります。
- ファイルサイズ: 高精細なメッシュモデルや高解像度のテクスチャを使用するとファイルサイズが非常に大きくなる傾向があります。
このように、3Dメッシュモデルは汎用性が高く、編集しやすいという大きなメリットがある一方で、特に微細なディテール表現や処理負荷の面で課題を抱えています。
新技術:3D Gaussian Splattingとは?
2023年に発表されて以来、急速に注目を集めているのが「3D Gaussian Splatting (3Dガウシアンスプラッティング)」という新しい3D表現技術です。まるで写真のような、あるいは現実空間をそのまま切り取ったかのようなリアルな3Dシーンを生成できることから、大きな話題を呼んでいます。
3D Gaussian Splattingは無数の「ガウシアン」で空間を表現

3D Gaussian Splattingは、一言で言うと「多数の小さなぼやけた楕円体(=ガウシアン)を使って3次元空間を表現する技術」です。
従来のメッシュモデルが点群から線と面を作っていたのに対し、3DGSは点群の各点をさらに表現力の高いガウシアンに置き換えるようなイメージです。そのガウシアンを重ね合わせて複雑な形状や質感を再現します。そのため、3DGSは従来のようなメッシュ構造を持ちません。
この新技術により、従来手法では難しかった半透明なオブジェクト、細かい葉っぱの集まり、複雑な光の反射といった表現が、驚くほどリアルに再現可能になりました。
メリット:圧倒的な再現性と高速レンダリング
3D Gaussian Splattingが注目される最大の理由は、その圧倒的な再現力と高速なレンダリングにあります。
- 圧倒的な再現性: 最大の特長は、写真と見紛うような非常に高い再現性です。光の反射や影の落ち方、物体の質感、煙や霧のような半透明な表現まで、従来のメッシュモデルでは困難だった複雑なディテールを忠実に再現できます。
- 高速なレンダリング: 一度学習が完了すれば、リアルタイムに近い非常に高速なレンダリングが可能です。これにより、大規模なシーンでもスムーズに視点を移動したり、インタラクティブに操作したりすることが容易になります。これは、特にVR/ARコンテンツやインタラクティブな展示などでの活用が期待される点です。
- 比較的軽量なデータ: 同程度の視覚的クオリティをメッシュモデルで実現しようとした場合と比較して、データサイズを抑えられる可能性があります。
デメリット:新しい技術ゆえの課題
一方で、3D Gaussian Splattingはまだ発展途上の技術であり、いくつかのデメリットや課題も抱えています。
- ソフトウェアやツールが未発展: 登場したばかりの技術であるため、対応ソフトウェアやツールはまだまだ少なく、扱うには専門的な知識が必要な場合も多くなっています。
- 編集・加工の難しさ: 現状では、生成された3DGSモデルを従来の3Dモデリングソフトでメッシュモデルのように細かく編集することはまだまだ困難です。
- 特定の用途への特化と汎用性の課題: その高い再現性はビジュアライゼーションには最適ですが、例えば精密な寸法計測や、CADデータとしての利用、物理シミュレーションへの応用など、メッシュモデルが得意としてきた分野では、まだ直接的な代替とはなりにくい側面があります。
新しい技術ゆえにまだまだ未成熟な側面もありますが、非常に活発な開発と研究が進んでいるため将来的にはこれらのデメリットは少なくなっているでしょう。
【実践比較】松本城を3Dモデル化:従来手法 vs 3D Gaussian Splatting
従来の手法と3DGSを用いて3Dモデルを作成してみます。今回は弊社が特別な許可を得てドローンで撮影した、国宝「松本城」で作成しました(撮影協力:松本観光コンベンション協会)。
3Dモデル作成には、産業用ドローンDJI Matrice 350 RTKと高解像度カメラZenmuse P1を使用して撮影した約2,000枚の空撮写真を使用します。
従来手法:3Dメッシュモデルで見る松本城
まず、撮影した写真データ(約2,000枚)を使い、代表的なフォトグラメトリソフトウェアの一つである「Reality Capture」を用いて3Dメッシュモデルを作成しました。
一目で分かる点として、松本城の堀にある水が全く再現されていません。従来の方法の大きなデメリットであり、再現するには人の手によってモデルの修正が必要です。

樹木も細かい部分が再現されておらず、従来の方法の苦手とする部分が表れています。

一方で、松本城の屋根の形状や石垣の質感はよく再現されているのが分かります。

新技術:3D Gaussian Splattingで見る松本城
次に、同じ写真データを使って3D Gaussian Splattingモデルを作成しました。
まず、従来の3Dモデルでは表現できなかった堀の水が綺麗に描写されていることが分かります。

樹木の葉っぱに関しても細かいディテールまで表現できています。

全体的に見て、従来の3Dモデルよりも写真に近い表現ができていることが分かります。
松本城での比較から見えてくること
実際に松本城という複雑な対象物で比較することで両者の違いがより明確に見えてきました。
従来型の3Dメッシュモデルは、全体の形状把握や汎用的な利用には十分な品質を提供しますが、特に複雑な構造物や微細なディテールの再現には限界があることがわかります。 一方、3D Gaussian Splattingは、現時点での編集性や汎用性には課題が残るものの、その視覚的な再現性、特にディテールの表現力においては、従来手法を凌駕する可能性を秘めていると言えるでしょう。
現状どちらの技術を選ぶべき?
これまでの比較を踏まえ、3Dメッシュモデルと3D Gaussian Splattingをどのように使い分けるべきかをまとめました。
3Dメッシュモデル
- 高精度な測量・地形モデル作成
- 測量分野では長年の実績があり、成果物の品質基準やワークフローがすでに確立。
- 精度検証や距離・面積・体積などの精密な計測に優れる。
- 構造物の詳細な点検・記録(橋梁・ダム・文化財など)
- ひび割れの幅や長さ、剥離箇所の面積など、具体的な寸法計測が必要な場合。
- 点検調書や報告書に添付する、定量的なデータとして活用する場合。
- CADモデルとの比較や、BIM/CIM連携を視野に入れる場合。
- ゲームや映像制作のアセット作成
- 既存のゲーム開発・映像制作ワークフローとの親和性が非常に高く、主要な3Dソフトウェアやゲームエンジンで標準的にサポートされている。
3D Gaussian Splatting
- リアルな景観・文化財のデジタルアーカイブ
- 松本城のような歴史的建造物の複雑な意匠、素材の質感、光の陰影まで忠実に再現し、まるでその場にいるかのような没入感のあるデジタルアーカイブを実現可能。
- 微細なディテールの記録: 肉眼では見過ごしがちな細部の装飾や、経年による僅かな変化も高精細に記録できる。
- ゲームや映像制作の背景・環境アセット作成
- 特にリアルな背景シーンを迅速に生成したい場合に有効。
3Dモデル作成・フォトグラメトリはASOLABにお任せください

弊社のドローン事業部「株式会社ASOLAB.」は、長野県松本市を拠点にドローン測量、構造物点検、各種調査、そして本記事でご紹介したような高精細3Dモデル作成まで、ドローンや地上レーザーを活用したソリューションをワンストップで提供する総合企業です。
ASOLABの強み
- 豊富な実績と専門知識: 測量や点検など各種業務で経験を積んだドローンパイロットが、お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案します。
- 最新技術への積極的な取り組み: 従来の3Dメッシュモデル作成はもちろんのこと、3D Gaussian Splattingのような最先端技術も積極的に導入・研究しています。お客様の目的に応じて、最適な3Dモデル作成手法をご提案可能です。
- 地域密着と全国対応: 松本市を拠点としながらも、ご要望に応じて全国各地へ対応いたします。
「ドローンでこんなことはできないか?」「最新の3D技術についてもっと詳しく知りたい」「大切な建物をを3Dデータで残したい」
ASOLABは、お客様の「やってみたい」を形にします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。